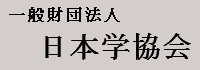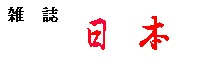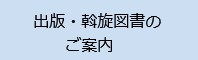『日本』令和7年12月号
国史の特殊性と一貫性について― 特に建武中興を主論点として
名越 時正 /元水戸史学会々長
終戦後新しく文部省から発行された国史の教科書に対して、嘗てティルトマン氏〔英国人ジャーナリスト〕は評して、それは「ただ人間の集合の物語であって、魂と習慣とその民族自身の信念を持った国家の物語ではない」と述べ、更に「若し日本の国家としての歴史が実際に此の教科書に叙述された如きものにすべて尽きるならば、日本は先祖の誇りもなければ子孫の希望も持たない驢馬(donkey)に似たものであらう」(『改造』昭和二十二年二月号)との痛言を与へられた。
この問題について、その後、日本人としてどのやうな論議検討がなされたかを私は知らないが、ここに氏がこの痛言の反面、英国人精神(自由)の伝統を誇る英国史、アメリカ的生活のあり方を伝統とする米国史を好例として示されたのを見て、日本の歴史書に命脈ある一貫性が表明されてないことについて、果たして実際さうなのか否かを反省をしてみたいと思ふ。
各国の国史の誇りといふ場合、それはその国の特殊性であると共に、又それが長かれ短かかれ、現在まで一貫して維持発展され、更に将来への希望を示すものでなければならないであらう。そしてこの条件は現在まで絶えず革命を繰り返すことによつて、行き方を常に変更しつつある国においては、見出され得ない処である。従つて我が国の歴史の特殊性について従来「革命なきこと」を第一にとり上げて考へて来たことは、此の点に於いて当を失したものではないのである。
ところが、この点について羽仁五郎氏は、国史の特殊性として「真実の徹底的な革命がなかったといふこと」を率直に認め乍ら、その理由を奴隷制、封建制または半封建的資本主義的帝国主義の国家の支配階級が「日本の革命をつねに不徹底におはらせた」と、全然今までと反対の立場からこの特殊性を批判してゐるのである(『新人』昭和二十一年四月号「日本歴史の特殊性」)。
この説についての詳しい批判は別の機会に譲るとして、この説一つの特徴は階級の下に国民を無理に引きちぎつて支配者と対立せしめてゐることで、国民の間に於いて革命を否定しようとした意思と事実とを隠蔽抹殺したり、技巧的に歪曲したりしてゐることである。
このことと関連して和辻哲郎博士がかうした問題を取り上げて、七百年の間、武家が人民を皇室から引き離してゐたやうな時代でも、革命が成功しなかつたのは何故かといふ問題を論じてゐる。武力なしに持続し得たその権威といふものが「国民の総意の表現にほかならなかつたからである」と説明したのは、一応考へるべきことで、右の羽仁氏の所感の一部を叩くものである。
しかし、深く考へるならば、これは民主革命が行なはれなかつた理由の説明にはなるかも知らぬが、あくまで一系の皇室と伝統を護りぬかうとした力を何ら説明し得ないばかりでなく、革命否定の為の強力な行動の由つて来るところを明らかにするには極めて薄弱な立論といはざるを得ない。
しかし、我国には革命が行はれようとしたことは決してなかつたのではない。皇位を得んとする者が国民の中にあり、伝統を倒さうとした場合があつたことは事実である。その際、革命を否定した理由は何であるかを考察するに当たつて、我々は我国の革命を防止した理由が、支配者の人民抑圧の為ではなく、反対に人民擁護の為であり、国運の発展を目的としたものであることを明らかにしなければならない。その一つの例は大化改新である。
大化改新が国家の飛躍的発展と国民生活の安定保護を主眼として、非常なる気魄と熱意とを以て断行されたことは歴史の一大光明であるが、この改新は一面に於いて古代末期以来の豪族による革命的機運と秩序破壊の危機を芟除(さんじょ)せんとしたものであることは周知のところであらう。
聖徳太子に於いても、孝徳天皇、天智天皇に於いても、蘇我氏達の革命的企図を抑圧したのは、かかる貴族が人民を搾取(さくしゅ)しつつあつたからである。「国司国造百姓に斂(おさ)めとること勿(なか)れ」と命じ、官吏として「忠君仁民」をモットーとせしめたのも、上宮大郎媛(うえつみやのおおいらつめ)をして「蘇我臣専に国政を擅(ほしいまま)にして多に無礼を行す(中略)何に由りてか意の任(まま)に悉(ほしいまま)に封民を役(つか)はむ」と痛憤せしめたのも、大化の詔に国司を戒めて「他の貨賂を捕りて民を貧苦に致さしむることを得ず」と厳命されたのも、すべて人民の撫育政治理念のあらはれでなかつ たものはない。
破壊者・搾取者を除いて伝統を擁護すると共に、民政を安定し、国家の発展を期した大化改新の成果が、上代盛時と思慕される奈良・平安の盛運を導いたのは、この故に当然なのである。
しかし、平安末期に至つて、公卿の堕落による政治の腐敗が極に達せんとしたとき、頼朝が起つて武家の支配を確立したことは、治安恢復のためにはその功を認むべきであらう。だが、石井孝氏の言ふごとく、「『律令政権』に対し、この『封建革命』はなほ『妥協的』であった故に、多分に古代的であり、したがって純粋に『中世的』ではなかったが、その故にこそ、当初に於いては否定の力を強く起(た)たせしめなかった」(『日本歴史』昭和二十四年六月号「日本史上に於ける中世と近世」)。
しかるに、北条氏によつて引継がれた武家の政権が次第にその妥協性を捨て去り、「革命性」を露呈して来れば、もはやこれを容認することは出来ない。そしてこの革命的風潮は思想に於いて「異朝ニハ文王武王臣トシテ無道ノ君ヲ討シ例アリ」とて、湯武を口実とし「戦国ノ時ニハ孔孟用ルニ足ズ」として、道義を捨て、人民の生活を無視したとき、後醍醐天皇自らかかる現状を打倒して革新を決意されたのである。
建武中興は武家革命の防止であると共に、又、仁政の確立による国家の発展に対する非常の努力である。処がこの建武中興の理想又は実際については、今日とかくこれを無視し、誤解し、或いは誹謗(ひぼう)する声さへあつて混迷愈々国史を疑はしめる懼(おそ)れがあるので、一応これを明らかにしなければならぬ。何となれば、この問題こそ国史の一貫性を物語るよき題材だからである。
誤りといふのは中興の理想即ち後醍醐天皇の御抱負を単に倒幕のみと解し、而もそれは文保の御和談、立太子の問題に関して幕府の干渉、反対に憤激せられての事とする説である。これによれば、倒幕の企ては天皇の私情に出たものに過ぎない。
これについては平泉澄博士の痛駁(つうばく)があつて、文保の御和談なるものはもともと成立せぬ故に、これを無視せられて、幕府の反対を憤られたといふのは全くの誤りとなる。立太子の問題については、その以前に既に正中倒幕の変あるを以て、これ又原因とはなり得ぬことを明らかにされ、その御理想は御父後宇多天皇より継承され、更に溯つては後鳥羽上皇の御意志に淵源するもので、延喜天暦の聖代即ち上代の盛時に復古せんとする国家中興の革新運動であることを明らかにされたのである(『建武中興の本義』)。
朝廷に於けるこの復古の理想の継承を看破し得ぬか、又はこれを無視して中興を考へるならば、単なる政権相奪か、封建制度の変容に起因する北条氏の自壊作用としか見られないのである。
伊東多三郎氏が「表面では公武の間の政権争奪戦であったが、社会史から見れば、封建制度の荘園的基礎から守護領的基礎へと移り変る転換期であって、ここにこそ真の歴史的意義を認めることができる」と述べられる(『日本封建制度史』)のは、一つの観点であつて、右に述べた理想を無視して批判するのは学問的欠陥がある。
さうかと思ふと、復古の理想は認め乍ら、政府の表面に立つた後醍醐天皇をとりまく大宮人たちは、四百年以上も昔の延喜の盛代にあこがれた。しかし、歴史の歯車を逆転させようとする大宮人たちの意図は、すでに鎌倉政権をも桎梏(しっこく)として打倒した武士の意図するところとは正反対であつたとして、その失敗を当然のこととする説が存在する(石井孝「日本史上における『中世』と『近世』『日本歴史』二十四年六月号)。
封建制度を否定したことを歴史の逆行として嘲笑(ちょうしょう)するならば、大勢に順応する他はないといふことになる。中興が決してそのままの「復古」でなく上代を理想とする革新であつて、種々新政が活発に行はれたことを忘れてはならない。
かうした妄説はその他数尽きないのであるが、最早取り上げるにも及ばぬであらう。歴史への逆行も恐れず、反対にも屈せず、大敵を前にして生死を顧みず、この理想の実現の為に敢然と戦つた天皇、及び公卿武家たちの強烈なる意志こそ国史上の重要な力として感得しなければならぬであらう。
鎌倉幕府の滅亡は一部の反北条的武士勢力の力によるところ少なくはなかつたが、これは伊東氏のいふ如く、朝廷がそれを利用して初めて倒幕が成功したのではなく、むしろ逆にかかる武士が朝廷の力に便乗することにより、自己を全うしたのであつた。そして、かかる武士こそ、建武の新政を僅か三年にして挫折せしめた張本人に他ならない。
「一たび軍にかけあひ、或は家子郎従節に死ぬるたぐひもあれば、わが功におきては日本国を給(たまえ)、もしは半国を給(たまい)てもたるべからず」(『神皇正統記』)等といつた武士共は、中興の理想などその片鱗も解し得なかつた無学の便乗者だつたのである。真摯(しんし)な改革の当事者は、常にかかる存在に苦しめられねばならない。
院政、摂関政治、武家政治を悉く廃し、上代を理想として儀礼道徳を立て、民生を苦しめる関所を止め、米価を調節する等活発に仁政を布いた中興政府はかくて足利高氏の叛乱の為に、武家の貪欲の為に崩壊したのである。
しかし一度(ひとたび)中興が挫折して、それで一切が終焉(しゅうえん)してしまつたならば、理想の価値は半ば失はれ、中興の歴史的意義は必ずしも大とは云へないであらう。新政はたしかに失敗はしたが、その理想は高氏の叛によつても倒されず、後醍醐天皇の崩御によつても終はらず、南北合一成つても消滅せずして、永く歴史を貫道し、明治維新王政復古の業となるのであつた。
室町時代を通じて、足利氏の革命的野心が封ぜられたのも、戦国時代下剋上の風潮が至高の権威を犯さなかつたのも、徳川氏の中央集権的封建制が尚京都を除外して敷かれ、幕末に於ける幕府打倒、危機打開の忠とならしめたのも、中興の理想の超時代的貫流に外ならないのである。だから中興を中心に見れば、それは上代を理想とすると共に、後世まで方向を与へた一つの力となつてゐるのである。
それは国史の縦断面である地方史に於いて、同様にその脈絡を明瞭に露呈する。そしてわが常陸の歴史に於いてそれは特に明らかである。佐竹氏の蟠踞(ばんきょ)する常陸は決して中央政治の浸透した地方とは思へない。むしろ鎌倉の勢力下に置かれた有力な地域であつた。
しかし、ここに中興の理想が点火されたのは、楠木正家、藤原藤房、北畠親房一族等の努力によつたものである。これに協力した那珂、笠間、小田、関、下妻、伊達、その他の諸氏は、小田氏を除いて、その家系に於いても、経済的地盤に置いても微々たるものに過ぎず、当時全国に於ける足利氏の勢力の増大を鑑(かんが)みるならば、高氏に親を通ずるの利が悟られぬ筈はなかつた。
しかし、これらの諸氏の中には一、二を除けば、大勢非なる日にも志を曲げず、兵糧断絶して飢ゑが迫つても尚屈せず、悉く生命を失ふまで、足利と戦つてゐるのである。
このことは、ただに官軍の有力者の保障を得んことを期待してのことのみでなく、親房はじめ熱烈なる指導者の導くところが至高の理想であり、それが伝統的道義の志と結び付いた強固なものであつたからこそ、思想的、経済的逆境に屈服せしめなかつた根本の所為としなければならない。
中興の失敗によつて雲散霧消することがなかつた理想追求の意志は、道義の裏付けがあつたのである。革命否定の根源力は、即ち道徳価値の変更を拒否せんとする意志の上に生ずるものであつた。それを最も明確にあらはしたのは『神皇正統記』である。古代上代を通じて、変更磨滅することのなかつた人倫関係を此の書ははつきりと説いてゐる。
瓜連、小田、関、大宝の諸城もその他の諸城も今なほその遺跡をとどめて、その悲壮なる道義の力を今に物語つて居り、それは単なる史蹟には非ずして、時の変に左右されぬ、脈々たる伝統の命脈を存し、今日といへど、経済的貪欲に屈せず、道徳を守り義理を尊ぶの風潮をその郷土にとどめてゐるのはその為である。
近世水戸藩の思想史上に残した作用は、その道義性の感得継承に他ならない。『神皇正統記』が『大日本史』及び後期水戸学派の準拠となつたことは、諸書を繙(ひもと)くとき誰しも感銘する処であらう。志士の行動が王政復古の最も大なる力であつたことを認めるならば、そしてその志士が水戸藩の思想に感発したことを認める以上、建武中興と明治維新を結ぶ脈絡を否定する者はあるまい。
それのみか、「志士は歴史の歯車を逆転させた」中興の協力者を行動の指標となし、封建的桎梏(しっこく)の中に精神の自由をもとめつつ、その古人の悲運に涙しつつ、伝統の存続のために一切を惜しまず、封建的支配者たる徳川氏を倒し、新しい時代を開いて行つたではないか。
我が国史の特殊性である「革命の行はれなかったこと」は決して偶然ではない。支配者が之を拒否したのでもない。もちろん一部には革命を企てる者の存在を否定することは出来ないが、かかる者を排除した力は、必ずしも実勢力を有しなかつた皇室を強力に支持する国民の道徳存続の念願に出づるものであつた。
道義の伝統、それは表面的には礼儀となつてあらはる。外国人の見た日本人観にこの点を取り上げた処が多いのは歴史学者の高柳光寿君の論ずる所である。ザビエルが「此国の人は礼節を重んじ、一般に善良にして悪心を懐かず、何よりも名誉を大切にすることは驚くべきことなり」(『耶蘇会士通信』)と賞したのも、この為である。
時の変化、世の推移は、人心の易(かわ)りに於いて、最も深刻なる感銘を我々に与へる。而してその人心の易りは理想の一変であり、道徳価値の変換である。しかし、由来、人の根本的理性と感情に根ざす道徳は、表層の変化によつて果たしてたやすく放棄され転換されるものであらうか。
動物的本能を人間性と解し、自由の限界を廃棄せんとする機械的革命理念が対立的争闘を生まぬ筈はないのである。破壊的革命の排除は、同時に人間倫理の維持であり、小にしては個人一家、大にしては社会国家世界の秩序を確立する根源である。
疑はれんとし、否定されんとする国史を凝視反省することは、今日吾々の当面の問題に、一道の解決路を開かしむる準備とならうことを、私は浅学乍ら確信せずには居られぬ。