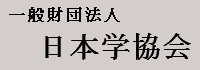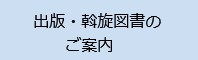『日本』令和7年9月号
大東亜戦争の淵源 ― 資料が語るその史実 ―(九)大統領は真珠湾へとつながる運命的な第一歩を踏み出した
田村一二
時を遡り、更なる「淵源」に迫る
一九四一年十一月二十五日のスチムソン日記から筆を起こし、論考を重ねてきました。スチムソン日記は圧巻であり、同日記について「両院委員会の集め得たる史料中の白眉(はくび)であり、日米の交渉一転して開戦に至る転機の指標」と平泉澄博士の喝破する所です。
「アメリカがさほど被害を受ける事無く、いかにして日本が最初に発砲するように誘導するかだ」と語るルーズベルト。なぜ斯(か)く迄して日本を戦争に引き摺り込もうとしたのか。以後、この疑問を解明するため、時を遡り、「大東亜戦争の淵源」に迫っていきます。
一 ルーズベルトの初当選― 国際主義から孤立主義への転向
一九三二年十一月、世界恐慌の嵐が吹き荒れる最中(さなか)の大統領選挙戦で、ルーズベルトは華々しいニューディール政策を掲げて、現職大統領フーバーを破って第三十二代アメリカ大統領に初当選しました。
ルーズベルトが初当選できたのは、ニューディール政策を掲げただけでなく、全米に一大メディアを持つ「新聞王」ウィリアム・ランドルフ・ハーストの支持を得たからです。支持を得るために彼は、第二十八代大統領ウイルソンから受け継いだ「国際主義」 注1の政治信条を隠して、「孤立主義」 注2へと転向したように見せたのです。それを公式に明言したのが、同年二月二日、ニューヨーク州農民共済組合での演説です(ビーアド『「戦争責任」はどこにあるのか―アメリカ外交政策の検証 1924-40』開米(かいまい)潤・丸茂恭子訳、一〇七―一一六頁、藤原書店、二〇一八年。原題"American ForeignPolicy in the Making 1932-1940" 一九四六年)。
注 2 米国の場合、国際連盟加入の拒否、ヨーロッパ及びアジアの紛争への不介入、不干渉、目的に適した諸施策による中立および防衛、互恵を基本として諸国との友好 的な外交政策を推進する。
そして、民主党の大統領候補指名を勝ち取り、初当選することができたのです。ルーズベルトは、自身の政治信条を偽って初当選したといえます。このことが、以後のルーズベルトの外交政策の外観と実態とが異なるものとなっていく大きな要因となるのです。
二 真珠湾へとつながる運命的な第一歩
「一九三三年三月、ルーズベルトが第三十二代大統領に就任した時、日米開戦は既に決定づけられてゐた」(『藝林』昭和四十四年十二月、二六八頁、藝林会)と指摘するのは、日本文化大學名誉教授井星英氏です。この指摘について、解明していかなければなりません。
就任に先立つ二ケ月前、次期大統領ルーズベルトは、フーバー政権の国務長官スチムソンと私的な会談を行いました。その時、ルーズベルトは非常に重要な決断をスチムソンに伝えます。
資料 一九三三年一月九日、フランクリン・D・ルーズベルト次期大統領は、ハイド・パークでスティムソン氏と昼食をともにした。その際に極東においては「スティムソン・ドクトリン」 [注]を採用する方針を明らかにした。この時、大統領は真珠湾へとつながる運命的な第一歩を踏み出したのだった。
(ビーアド『ルーズベルトの責任』六〇六頁)
㈠ 資料の意義
スチムソン・ドクトリン(満洲不承認政策)は、日本の国益とは全く相いれない政策です。満洲経営は、国策の心臓部に匹敵し、その不承認という事であれば、例え誰の構想であろうと看過できません。ルーズベルトが極東外交政策として採用することについて、側近が日米開戦の危険性が高いことを指摘したにも拘らず実行したのです。大東亜戦争の淵源を考える重要な資料です。
㈡ 解 説⑴ 「スチムソン・ドクトリン」とは
同ドクトリンが発表されたのは、ルーズベルト初当選前の一九三二年一月七日に遡ります。その内容は
① 一九三一年九月十八日に勃発した満洲事変以降の日本の軍事行動を非難し、パリ不戦条約に違反するいかなる行動も認めない。
② 中国への軍事行動から生じた条約や中国大陸における勢力圏の変化を承認することを拒否し、アメリカの中国における条約上の権利・権益を侵害する取り決めを一切認めない、すなわち満洲での日本の行動を一切認めない「満洲不承認政策」。
一九三二年当時、フーバー政権の国務長官スチムソンが、「満洲での日本の行動を行き詰らせるため取り組みの一環として実行しようとして考えた」(ビーアド前掲書、二五二頁)ドクトリンです。では、スチムソンは、この政策をどのようにして実行しようと考えていたのか。ビーアド博士は次のように指摘します。
スチムソン国務長官の構想には、経済制裁を課すこと、制裁を強制するにあたって可能なら他の国々と緊密に協力すること、もし制裁が失敗に終わった場合、ほぼ確実に戦争をも受け入れる意思が含まれていた。言い換えれば、スチムソン・ドクトリンは一九四一年に実行され、立証されたことを一九三三年時点で正確に意味していた(ビーアド『「戦争責任」はどこにあるのか』、一九五頁)。
⑵ フーバー大統領の警告
一九三一年末、フーバーは閣議で、「われわれが満洲の紛争に関連する問題を巡って戦争する必要はない。私はアメリカ国民の生命を犠牲にするつもりはない」。そして「戦争以外のあらゆる影響力を行使する道徳的義務がある」と語った後、「しかし、これが限界である。われわれは他国と協同して戦争に向かうことはないし、如何なる制裁にも、経済的制裁であろうと、軍事的な制裁であろうと、加担しない。それは戦争へと続く道だからである」。フーバー大統領自らが、かくも明確かつ適切に示したのです(ビーアド前掲書、一九五―一九六頁)。
スチムソン・ドクトリンが発せられたのはその直後です。これはアメリカの外交基本政策を大きく破るものですが、フーバーの外交姿勢がどうであっても、スチムソンは政権の国務長官であり、一九三一年から三二年にかけて満洲問題の対処上で陣頭にたっていたのです。フーバー大統領は、「戦争へと続く道」となるような制裁やその他の方法に、スチムソンが従事していることを知り、内密のうちに同長官を制止し政権が終わるまで、この姿勢を取り続けたのです。
⑶ スチムソンの働きかけと英仏の反応
しかしスチムソンは、不屈な粘りで日本を手詰まり状態に追い込もうと、国際連盟の友好諸国や極東に重大権益を有する英・仏両国政府に働きかけます。特にイギリスについてスチムソンは、追随して同様な方針を世界に向けて発信するだろうと予想していました。
ところが、英、仏は、スチムソンの申し出には冷淡で、丁寧に中立化の方向へ舵を向けのです。最終的にはスチムソンの考えている敵対行動を含む危険、即ち極東に戦争を起こす危険を冒すことを拒否しました。
⑷ スチムソン・ドクトリンの正式決定
一九三三年三月七日、政権発足直後の閣議において、ルーズベルトは、スチムソン・ドクトリンを次期極東外交政策とすることを正式決定しました。同ドクトリンが、一高官の構想から国家としての正式な極東外交政策となったのです。アメリカ歴史学者のチャールズ・C・タンシル教授は、同ドクトリンの危険性を次のように指摘しています。
「学者は、ルーズベルトが『不承認ドクトリン』を採用した危うさを過小評価しているように思える。この思想は火がつけられた長い導火線のついた爆弾であった。導火線の火は数年かけて、ついにその爆弾を爆発させ、第二次世界大戦となった」(タンシル『裏口からの参戦・上』渡辺惣樹訳、一七頁、草思社、二〇一八年、原題"Back Door to war:The Roosevelt Foreign Policy 1933-1941" 一九五二年)。
同著は、主として国務省に残された一次資料に依拠した歴史学の正統手法に則った本格的な研究書です。
一流の歴史学者であるビーアド博士とタンシル教授の見解はほぼ同一で、日本の満洲政策と経営、アメリカ外交の歴史、支那の国情に対する深い研究からスチムソン・ドクトリンの危険性を熟知していたのです。
三 アメリカのソ連承認
アメリカ大統領ウイルソンは、ロシアが革命によって全く異質な国となり、その政治形態や経済的制度がアメリカの平和、倫理観、礼節の概念と一致しない政府で、非合法な存在であるとして、承認しませんでした。以後、ハーディング、クーリッジ、フーバーの各大統領はその路線を踏襲し続けていました。
一九三二年三月、満洲国が建国されて、ソ連と国境を接することとなり、軍事的緊張は増大してきました。さらにソ連は、満洲へ共産勢力の浸透を強め、外蒙古(今のモンゴル)を支配下におき、新彊への進出は著しく、北支への侵入も狙っ敵として、日米の接近を最も怖れており、対米接近工作を強力に進めていました。ソ連の戦術は、アメリカにとって日本はいかに危険な存在であるかを誇張して、アメリカを誘い出すことにあったのです。
一方、承認問題について、ルーズベルトの心中を看破していたルイス・フィッシャー(アメリカのジャーナリスト、一八九六―一九七〇年)は、次のように記しています。
資料
次期アメリカ大統領ルーズベルトは、日本のアジア進出と米ソの関係性を考え、大統領就任前から、(承認に反対していた)「フーバー、スチムソン、カッスル[注]の蜘蛛の糸」を払いのけ、ソ連政府を承認しようと決心していたのです。( )は筆者 ( ルイス・フィッシャー『平和から戦争への道―スターリン外交の25年 ―』吉沢清次郎訳、三五九頁、昭和四十五年刊、時事通信社、原題"RUSSIA’S ROADFROM PEACE TO WAR Soviet Foreign Relation,1917-1941" 一九六九年)
注 フーバー政権国務次官(一八四九―一九三五年)
㈠ 資料の意義
「ルーズベルトの関心事は日本の膨張」(同著、三五九頁)であり、就任前にはソ連承認の意図があったことを明確に示している資料です。駐日アメリカ大使グルーはソ連を承認した効果を、「ルーズベルトは名手を打った」(タンシル前掲書上、二二四頁)と日記に記しています。「名手」とは、いざという時、アジアにおいて日本を抑制でき、包囲網ができ上がるという意味です。
㈡ 解説承認の決断は重大事だったにも関わらず、一九三三年十一月十六日、ルーズベルトは対ソ債務に関して形ばかりの交渉を済ませ、殆ど無条件で承認したのです。
資本主義の立場からすれば日米提携して反共防壁を形成すべきところ、全く逆の決定をしたのです。日本はアメリカとの関係改善を望んでおり、共産主義の防壁として共同で対処する希望を強く持っていました。
共産勢力が満洲、支那を席巻しているこの時点でのソ連承認は、共産勢力の恐るべき怒濤(どとう)を支那に引き入れることになりました。ルーズベルトは、ソ連を承認して、日本の願いに背を向け大きな痛手を与えたのです。
第三十一代アメリカ大統領フーバーは、ソ連承認によって、起こった世界の混乱を次のように述べています。
( ハーバート・フーバー著、ジョージ・H・ナッシュ編、『裏切られた自由―フーバー大統領が語る第二次世界大戦の隠された歴史とその後遺症・上』渡辺惣樹訳、一八一―一八二頁、草思社、二〇一七年、原題"FREEDOM BETRAYED" 二〇一一年)
四 隔離演説
ソ連承認後、ルーズベルト大統領は、中立法を成立させ、「如何なる紛争にも巻き込まれない」という声明を幾度も表明し内政に専念して「孤立主義の路線」を固く守ります。そして対外的には厳正中立に徹し続けて、一九三六年末には第二期大統領に再選されまた。
一方日本は、昭和八年五月、満洲事変終結の塘沽停(タンクー)戦協定を締結して、昭和十年五月には日支間での大使交換をするまでに至ります。日支関係は表面的ではありましたが、この頃が最善の時期でありました。
しかし、日支親善関係の進みとは裏腹に北支の混乱は収拾がつかず、その要因は支那共産党の動きにありました。昭和十年八月、支那共産党は「救国抗日宣言(八・一宣言)」を発表して日本打倒を明確にします。当時、蒋介石は共産党には厳しく対処し剿共(そうきょう)戦を展開しており、昭和十一年(一九三六)十一月、第六次剿共戦ため西安へ入りました。そして十二月十二日、突如として、張学良によって蒋介石が監禁されるという西安事件が勃発します。蒋介石は殺される寸前で釈放され、釈放の条件は、「国民党と支那共産党との合作」です。これが盧溝橋事件の伏線となっていきます。
かくして昭和十二年七月七日、盧溝橋事件が起こり、八月、戦線は上海に広がり、さらに拡大して九月、「支那事変」と呼称することが決定されました。国際連盟は、国民政府の提訴を受けて九月二十八日、日本の飛行機による支那無防備都市への爆撃を不法とする決議を採択し、十月六日には「連盟での議論によって解決を図ること」や、「連盟加入国は個別に支那の援助を考えるよう」勧告する決議を採択しました。
ルーズベルトは、日本非難の連盟審議を見て取り、今や日本は孤立無援に陥ったと判断し、十月五日、孤立主義の牙城、シカゴに乗り込んで「隔離演説」を行うのです。演説全文は長いため抜粋して紹介します。
資料 隔離演説(抜粋)
〇 激しい戦争で生命や財産が破壊されています。もしこうしたことが世界の他の地域でも起こるならば、「アメリカは免れるだろう、アメリカは情をかけて貰えるだろう、西半球は攻撃されずに平穏かつ平和裏に文明の神髄と倫理で維持できるだろう」などと、決して想像してはなりません。
〇 平和を愛する諸国は、単に孤立や中立を守ることでは逃れることはできない。今日の国際的な無秩序状態と不安定を生んでいる条約違反や、人間の本能を無視した行為に、一致協力し反対しなければならないのです。
〇 世界には無法状態という疫病が広がっています。肉体を蝕む伝染病が広がり始めた場合、地域の共同体は、その健康を感染の拡大から守るため、病人を隔離することを是認し、協力します。戦争とは伝染するものです。
〇 アメリカは戦争を憎みます。アメリカは平和追求する取り組みに積極的に参加するのであります。
(ビーアド前掲書、二五五―二五九頁)
㈠ 資料の意義
この演説は抽象的で、しかも国名は出てきませんが、ルーズベルトのいう「世界の無法状態という疫病を広げている国、即ち世界の平和を乱す国」とは、日・独・伊の三国です。しかし「大統領のスピーチの主たる対象は日本」(タンシル前掲書下、三六頁)であり、「隔離」という用語は、大統領が勝手に挟んだものです。その理由は、支那事変の激化・拡大に対する「主として日本への警告を意識したもの」(タンシル前掲書下、三六―三七頁)だったのです。
ルーズベルトの関心は、「日本の膨張の阻止」であり、この隔離演説は日本を隔離・孤立させるという日本敵視を意図したものでした。
㈡解説この「隔離」の意味をルーズベルト政権下で国務次官を務めたサムナー・ウェルズ(一八九二―一九六一年)は、回想録で次のように書いています。
一九三七年には、彼(ルーズベルト)は日本の示す脅威の力に心を奪われていた。そのことはまぎれもなく明らかである。その夏の初め頃、初めて私に次にように話した。日本がアジア征服の政策を続ければ、海軍防壁(a naval barrier)を構成することもありうる。この海軍防壁の構成のことを、彼は後に「隔離」と述べたのである(ザムナー・ウェルズ、 "Seven Decisions that shaped History" p8、一九五一年、国立国会図書館蔵)。
隔離の意味が、「海軍防壁」であることが明らかになりました。その具体的な意味が更に明らかになっていきます。
五 パネー号事件とルーズベルト
「一九三七年夏の始め頃」と言えば盧溝橋事件が起きた頃であり、以後、拡大の一途を辿って十二月十二日、南京事件の前日、南京付近の揚子江上に停泊していたアメリカ砲艦パネー号が日本軍の誤爆によって撃沈されるという「パネー号事件」が起きてしまいます。ルーズベルトは、日本の出方如何(いかん)によっては、パネー号撃沈の罪を鳴らして直ちに対日武力発動に踏み切る決意を固めていました。
日本は、政府、軍を挙げて最大限の誠意をもって謝罪し、民間にあっても在日米国大使館には日本各界の代表者の訪問、手紙、義捐(ぎえん)金が殺到して陳謝の言葉と遺憾の意を表したのです。さらに陛下は十四日朝、侍従長を首相のもとに御差遣(さけん)あそばされ、思し召しの程を、大統領からのメッセージが届く前にアメリカに伝達するよう命じられたのです。あわや日米開戦に発展する危機をすんでの所で防ぐことができました。
しかし、パネー号事件が、陛下を始めとした日本側の誠意ある丁寧な対応、そして賠償金、謝罪文書で終ったわけではありません。大統領の心中では、日本を信用できないという疑念が深まっていきます。この感情をルーズベルトが持っていることは、すでに十月五日 の隔離演説ではっきりしています(タンシル前掲書下、二五〇頁)。
更に「対日武力発動に踏み切る決意」を知ることができるのは、事件後の十二月十七日の閣議の様子を、内務長官ハロルド・L・イッケス(一八七四―一九五二年)の秘密日記に次のように記されているからです。
「隔離」とは「海軍防壁の構成」であり、具体的には「日本封鎖線」であることを、ルーズベルト自身が述べているのです。支那事変に手を取られている日本に対して米英が共同して封鎖し、経済制裁を科し、国力の枯渇を企て、日本打倒の爪を研いでいたのです。
六 インガソル海軍大佐への密命
ルーズベルトは、「隔離」を実行するに当って日本打倒の手を着々と打っていくのです。米英は不可分の関係にあり、十七日の閣議後の二十四日、戦争計画部長ロイヤル・E・インガソル海軍大佐(一八八三―一九七六年)は、密命を受け極秘裡にイギリスに到着します。表面上は上官の命令ですが、ルーズベルトの個人訓令です。インガソルへの密命が次の資料です。
資料
日本との戦争になった場合、(米英共同で)何ができるかの検討、および指揮命令系統の調整、武官の相互派遣、暗号等の準備である。 ( Pearl Harbar Attack Hearings Part9, p4273-4274 (国立国会図書館蔵)
㈠ 資料の意義
米英が対日開戦の場合に「指揮命令系統の調整」とは、作戦協力や使用艦艇、航空機等も規定しておくことも含みます。これらが軍のみの命令でできるはずはなく、その上位には政治協定が必要です。しかし、それを抜きにして討議された所以(ゆえん)は、ルーズベルトの「個人訓令」から発しているからに他なりません。インガソル大佐は「作戦目標は明確に日本だけに絞られていた」と、議会真珠湾調査委員会で証言しています(前掲資料、四二七四頁)。対日戦に備えていたことを示す 資料です。
㈡ 解説ウイルソン大統領は、第一次世界大戦の宣戦布告を連邦議会に求める前には、既に米英の打ち合わせを済ませており、海軍諸計画はでき上がっていました。ルーズベルトも同様な布石を打つのです。インガソル大佐は、更に次のように証言しています。