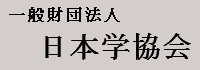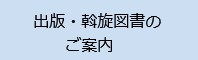『日本』令和7年7月号
巨大共産主義国の大変革(中)― 中国の大変革(その一) ―
吉田和男 京都大学名誉教授
中華人民共和国の誕生
もう一つの社会主義経済の大変革をしたのが、中国である。中国では毛沢東の人民解放軍が国民党軍との内戦に勝利し、一九四九年に中華人民共和国建国宣言となる。国民党軍は台湾に逃げ込み中華民国政府を置き、中国の代表権は中華民国政府にあるとされていた。
しかし、一九七一年に国際連合総会で中華人民共和国が中国の代表であると決議されたことに伴い、一九七二年にニクソン米大統領が中華人民共和国を訪問して、米中の国交が開かれる。そして、日本を含む大多数の国が中国の代表権は中華人民共和国にあるとして、中華民国政府とは国交を断絶する。国際連合においても中華人民共和国が中華民国と入れ替わり、安全保障理事会の常任理事国となる。そして、中華民国は国際連合から脱退した。現在、国交のある国は十二ヶ国に過ぎない。
中国は台湾の支配に軍事力を使うことを躊躇しないといい、台湾付近で軍事演習を行うなどの圧力をかけている。アメリカは台湾関係法に基づき、台湾軍に戦闘機などの武器売却などの支援を行っている。軍事力による現状変更は認めないと、第七艦隊を使って中国を牽制している。台湾問題は極東の安全保障問題として、我が国も無関心ではおられない。
人民公社による社会主義経済
中国の社会経済制度は、一九五三年から開始された人民公社の設立が基本となった。人民公社は従来の農業生産共同組合である合作社に工業、農業、商業、学校、民兵、地方行政などを一体化して、自力更生、自給自足を目指した組織とすることであった。このために、地主や富裕家の財産をすべて没収するという共産主義政策を行った。
これは、コミンテルンの指導では都市労働者から革命を進めるというのに対して、農村から社会主義体制構築を進めてゆくという毛沢東の思想を実行したものであった。一九五八年末には、全農家の九九%が人民公社に属している。また、企業の国有化も行われ、社会主義経済体制となる。
大躍進の失敗
一九五七年には、プロレタリアート独裁を批判した知識人等を弾圧し、共産党内の反毛沢東派を追放して、毛沢東の個人崇拝が定着した。
毛沢東の指導で一九五八年から「大躍進政策」が行われる。高度経済成長で十五年以内にアメリカやイギリスを追い越すことを宣言する。しかし、無能な共産党指導者層が実態を無視したノルマを課し、ノルマを達成できなかった現場責任者は過大な報告を行い、それに基づいてさらに過大なノルマをかけるという悪循環に陥る。
また、鉄鋼の大増産を目指して、人民公社にもノルマを課した。全国で原始的な土法炉(どほうろ)で鉄鋼を作らせた。しかし、土法炉に必要な耐熱煉瓦(れんが)がないので城郭や寺院などを解体して煉瓦を調達したため、歴史的建造物などが破壊された。
還元剤に木炭を使うので、大規模な森林伐採が行われた。そもそも鉄鋼生産の原材料がないため、鍋釜や農機具を溶かして鉄鋼生産のノルマを達成しようとした。できた製品も、六〇%が使い物にならなかったという。
また、人民公社という農村のコミューン化で生産意欲の減退もあった中で、三倍の収穫を得るために三倍の種を撒(ま)くという過度な密植を行ったため農業生産が低下し、一九五九年には、全国で大飢饉となった。餓死者は三千六百万人以上といわれている。
農民には無理な労力の提供要請があり、農業や生活の基盤が破壊された。国営企業による工業の発展にも失敗する。一九五九年に毛沢東は大躍進の失敗の責任を取り、国家主席を辞任する。
文化大革命
毛沢東の後任の国家主席になった劉少奇(りゅうしょうき)は部分的に市場経済を導入して、経済は徐々に回復に向かった。しかし、毛沢東は劉少奇らを修正主義と批判した。
一九六六年に、失脚していた毛沢東を支持する学生運動グループが紅衛兵と名乗り、毛沢東の復活を図る。毛沢東は紅衛兵に、劉少奇や国家副主席の宋慶齢をはじめとする実務派幹部を反革命の「走資派(資本主義に走る者)」として糾弾させた。
この運動は瞬く間に広まり、共産党の実務派やそれにつながる党員、さらには知識人、旧地主の子孫などが反革命分子として、紅衛兵によって暴力的につるし上げられる。大衆の面前で三角帽子をかぶらされ、自己批判をさせられた。若者を中心に「造反有理」をスローガンに、赤い毛沢東語録を手にして、走資派を糾弾する「文化大革命」という巨大な運動に発展する。
一九六八年には、多数の知識人などが、農村に学ぶべきとして「下放(農村部への強制移住)」をさせられた。文化大革命は共産主義革命を単なる生産制度の改革だけでなく、人の生きる道である精神の根幹を毛沢東思想によって変えて行こうとする運動であった。
文化大革命末期には、「批林批孔」がスローガンとなる。一九七一年に党中央副主席で共産党幹部のナンバーツーで文化大革命を推進した林彪は、毛沢東の後継者を狙って毛沢東暗殺を企てたという嫌疑をかけられて批判される。林彪はソ連へ亡命を図るが、飛行機事故で死亡する。
また、儒教は反革命思想であるとして批判され、多くの儒教文化財が破壊された。そして、焚書坑儒を行った秦の始皇帝が称賛された。
文化大革命の内実は、江青(こうせい)(毛沢東夫人で一九七三年から共産党中央政治局委員)・張春橋(ちょうしゅんきょう)(国務院副総理)・姚文元(ようぶんげん)(共産党中央政治局委員)・王洪文(おうこうぶん)(共産党中央委員会副主席)の「四人組」が共産党の実務派幹部を失脚させるための運動であった。
この運動は共産党も制御不可能となり、一九六七年九月に毛沢東は秩序回復を人民解放軍に命じ、紅衛兵と武力衝突が起こって、多数の紅衛兵が処刑された。この騒動で虐殺や内乱が起こり、その死者数は数百万人から二千万人ともいわれている。
一九七六年には毛沢東が死亡し、文化大革命の中核的存在であった「四人組」は文化大革命を煽った者として逮捕・裁判が行われ、死刑(執行猶予付き)や懲役刑となる。一九七七年の中国共産党全国人民代表大会で「四人組」の党籍が剥奪され、追放されていた実務派の党員の名誉回復が行われて、十年間ほどの文化大革命の大騒動は終結した。
鄧小平による改革
中国は「大躍進」と「文化大革命」という世紀の大失策を行い、長期の経済停滞が続いた。
文化大革命によって失脚していた鄧小平(とうしょうへい)が一九七七年に中央軍事委員会主席となり、全権を掌握する。鄧小平は一九七八年に日米を訪問して、中国の遅れを痛感する。鄧小平の決断により、同年の共産党中央委員会全体会議で改革開放の方針が決定され、経済改革が始まる。
一九九二年に鄧小平が、地方の巡回をした際に表明した「南巡講話」を契機として、一気に改革開放路線への転換が行われ、社会主義経済に代わる「社会主義市場経済」が新しい経済体制となった。実質的には資本主義経済への転換であった。
鄧小平は「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」として、共産党独裁を変えないが、経済は市場経済で行う改革開放政策を始める。既に一九八○年代には、農家に生産者責任制度が導入され、自由な生産と販売を認めた。これにより、郷鎮(ごうちん)企業(農家の設立した企業)」が生まれ、農村地域から経済発展がはじまった。「万元戸(年間所得が一万元を超える家)」が多数生まれ、農村から市場経済となり豊かになる。そして、一九八二年の憲法改正により人民公社は廃止された。
さらに、深圳(しんせん) ・珠海(しゅかい)・厦門(あもい) ・汕頭(さんとう)の四つの経済特区が設けられ、外資導入や自由経済活動が認められた。それをモデルに順次、経済開放都市を広げ、市場経済・資本主義経済が導入される。
ロシアではエリツィンによって国有企業を株式会社化して、株式をばらまくというような急激な民営化でオリガルヒを生んだのに対して、中国では大企業の国有制度を維持しながら、経営請負制度で経営の自由化が目指された。
国有企業に民間資本の導入を図り「共同所有」制度を始めた。起業も自由化されたので、現在の企業数は六千万社を超えており、国有企業の企業数は三十九万社で極一部となっている。ただ、国営企業の生産は経済全体の二割程度を維持して、経済成長を図る戦略的な産業政策を行っている。共産党独裁で共産党員の既得権を認めながら、市場経済化するという「社会主義市場経済」は成功したようである。
一九八五年頃から鄧小平は「先に豊かになれる者たちを富ませ、落伍した者たちを助ける」という「先富論」を改革開放政策の基本原則とする。
この結果、中国経済の経済成長はめざましく、短期間の内にアメリカに次ぐ経済大国となった。二○○○年のGDPは一兆ドル程度であったものが、二十年間以上も経済成長率が九%を超えた結果、二○二二年のGDPは十八兆ドルで日本(四兆ドル)を大きく追い越して、アメリカに次ぐ世界第二位の経済大国となった。やがてアメリカを抜くのではないかというような予測も生まれている。購買力平価では既に抜いている。
中国の一人当たりGDPも一九九○年には三百四十九ドルで世界第百三十四位の最低クラスであったものが、二○二二年には一万二千八百十三ドルで世界第六十六位にまで上昇している。貿易相手国では、アメリカへの輸出が四千二百九十七億ドルで全輸出の一九%を占め第一位であり、アメリカからの輸入は千五百五十三億ドルで全輸入の八・四%を占めて第三位である。
日本への輸出は、千三百七十三億ドルで六・一%と第三位であり、輸入は、千六百五十六億ドルで九%と第二位にある。日本の貿易相手国としても、中国は二○二○年の貿易額が三十二・五兆円で第一位である。中国経済は、日米経済にとっても重要な位置を占めている。
世界の貿易に占める中国の貿易の割合も一四・七%と世界第一位であり、世界の工場として大きな経済大国の位置に成長している。ただ、アメリカは中国との貿易収支バランスで、中国が大幅な輸出超過になっていることに神経を尖らせており、貿易摩擦を引き起こしている。
現実に、第一次トランプ大統領の時には米中貿易戦争を起こしている。二○二五年に再び大統領になったトランプは四月に中国に対して一四五%の追加関税を課した。そこで中国は直ちに一二五%の報復関税を課した。両国は五月にジュネーブで交渉し、「九十日間の関税引き下げ枠組み」で合意し、アメリカは中国に対し一四五%から三〇%に引き下げ、中国はアメリカに対し一二五%を一〇%に減税するという調整が盛り込まれた。しかし、これで決着したわけではなく、予断を許さない状況である。
中国は二〇〇一年にWTOに加盟しており、自由主義経済圏に移っている。しかしながら、中国共産党自身は健在であり、その政治的行動は、自由主義経済圏で培(つちか)われてきたルールとは異なった行動を見せることも少なくない。また、インフラ・鉄鋼・自動車など重要産業では国有企業が残っており、戦略的産業政策を行っている。戦後の日本が経済復興のために、財政投融資資金を使い、官主導で重要産業の支援を行った戦略的産業政策と似たようなものがある。
改革開放政策の中で一九八九年に世界の人々を驚かせたのは天安門事件であった。同年五月に、北京の大学生、市民が天安門広場に集まり、自由の女神像を持ち出して、鄧小平を最高指導者とする中国政府に民主化の改革を求めた。
これに対して鄧小平は人民解放軍を投入し、大惨事となった。ここでは共産党独裁は貫徹され、三百十九人が死亡した(実際には数百人から一万人にも及ぶという説もある)。鄧小平は、「これは反革命暴乱であり、鎮圧は正しかった」と述べたようである。中国は経済の自由化を進めながら、共産党独裁体制を強化すことになる。
習近平による独裁
改革開放経済政策は大成功を収め。人々の生活は飛躍的に向上した。しかし、共産党員の特権を残しながら資本主義経済を導入すれば、必然的に起こるのは「賄賂」である。
二〇〇二年に共産党総書記・中央軍事委員会主席に、翌年に国家主席に選出された習近平は「大虎も蠅もたたく」といって賄賂社会の撲滅を図り、共産党員の整理を行う。人民からは経済成長によって劇的に生活が改善されているところに、一部の共産党員の不正が摘発されたことは歓迎されて、大衆の習近平主席への支持は高まる。同時に、共産党内の政敵を叩くことになり、習近平独裁体制は強化されることになる。
二〇二二年の中国共産党全国人民代表大会では、三期目の再選はなく、六十八歳以上の者は中央政治局常務委員会委員にはなれないとしてきた慣例を破り、習近平は異例の三期目の総書記に再選される。そして、共産党の最高意志決定機関である常務委員会の委員に元秘書や元部下などを任命し、共産党のトップグループを身内で固め、習近平独裁体制を強化している。
習近平の経済思想
習近平主席のスローガンとして、マルクス、レーニン、毛沢東の「站起来(立ち上げ)」、鄧小平の「富起来(豊かになる)」の次に来るものとして、「強起来(強くなる)」を掲げて、経済・科学技術等の発展、国家のガバナンスの強化、環境・自然との調和、世界一流の軍事力の建設を追求しようとしている。
習近平主席の経済思想では、「新発展理念」が提唱されている。それは経済発展を引き出す「イノベーション」、都市・農村・各地域・各産業・経済・社会などの「協調」、「環境」の重視(グリーン)、「対外開放」、発展政策などの成果を全国民による「共同富裕」とすることである。これによって経済を牽引し、中国国民を豊かにする考えのようである。
中国国民の習近平主席への支持が高いのは、鄧小平の改革開放政策以降の高度経済成長によって豊かになったことによるのは間違いない。先に述べたようにGDPは十八兆ドルでアメリカに次いでおり、最近までの三十年間に約四十二倍になっている。
高度経済成長によって、年収二百万元(約四千万円)以上の富裕層は年率一五%の勢いで増加し、二○一五年までには四百万世帯を超え、富裕層の数で米国・日本・英国に次ぐ世界第四位に浮上している。中国人富裕層は若年層が多く、四十五歳以下の世帯が約八〇%を占めているようである。
二〇二二年時点での資産額六百万元(約一億二千万円)以上の富裕層は五百十八万世帯、資産額一千万元(約二億円)以上の「高富裕層」は二百十一万世帯であるといわれている。
二〇二四年のフォーブスの調査による資産十億ドル以上の超富裕者は世界で二千七百八十一人であるが、一位はアメリカで八百十三人、二位は中国(香港とマカオを含まず)で四百九十五人である。香港は六位で八十二人であり、併せれば五百七十七人である。三位はインドで百六十九人であり、米中がいかに突出しているかが分かる。ちなみに日本は四十人である。
現実に、格差を拡大しながらも各所得層で所得が拡大してきたことは、日本への中国からのインバウンドの爆買いや不動産の購入などから見ても間違いがないところであろう。こういった富裕層だけでなく、一九九〇年頃には一千万人程度であった中間層は二〇一三年には既に六億人を超えているといわれている。
しかし、習近平主席のいうように貧困層がゼロになったというのは、信じがたいことである。貧困層の定義が違うのであろう。年収が六百二十ドル以下を貧困層としているようである。
しかも、ジニ係数(所得の不平等度を示す指標)は〇・四六という推計もあり、世界的にもブラジル(〇・四七)、メキシコ(〇・四六)に並ぶトップグループ(中南米の平均は〇・四七)の格差大国である。人口の減少、高齢化で経済成長率が低下した時に、この不平等社会の不満が爆発しないともいい切れない。
ジニ係数が〇・四を超えるといつ暴動が起こっても不思議ではないという話もある。既に通常の資本主義国とはレベルの違う貧富の格差が生まれている。ちなみに日本のジニ係数は〇・三四であり、格差社会で有名なアメリカでさえ〇・三九である。平等度の高いスウェーデンは〇・二八である。「平等」が売り物の社会主義国で高度経済成長の結果、格差大国になっている。逆にいえば、「先富論」で格差を是認したことから、驚異的な経済発展をしたのである。
習近平主席の低所得者の所得を上げることで格差を減らすという「共同富裕」政策がどの程度成功するかの問題であるが、この格差が容易に解消するとは思えない。それが、中国国民の不満を高める可能性もある。