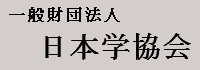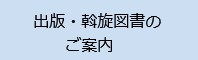『日本』令和7年5月号
(一財)日本学協会定例講演会生者と死者、そして伝統(下)― 生者は死者の声を聴きながら生きる ―
渡辺利夫拓殖大学前総長
我々の運命とは
これは比較的分かりやすい話ではないかと思うのです。つまり、生者も死者も、国家という文化的政治的な共同体の成員として生きているということです。私どもは、もう一つの運命として、生きている者も死んでいる者も、国家という文化的政治的な共同体の成員として生きていかなければならない。
皆さんパスポートをお持ちだろうと思うのですが、観光旅行や海外研修などで外国に出かけるときにパスポートを受け取ったはずです。このパスポートがなければ、そもそも日本を出国することも、外国に入国することも不可能です。
そのパスポートの扉の裏の頁にどのようなことが書いてあるか、こう書いてあるのです。日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。日本国外務大臣。
こう書いてある。英訳も載っております。
それで、皆さんがある国に入国するとき、入国審査官がこの英語を読んで、あなたたちが正当な手続きを経てこの旅券を所持して入国しようとしている日本の公民であることを確認し、そして入国許可のスタンプを押してくれるわけです。もうお分かりの通り、我々は日本人であり、日本国家の公民であり、その国家の公民であることを離れては、海外との交流はその入口さえ見出すことができない。グローバリゼーションの時代だといくら叫んでも、この事実は変わりようがない。国家とは、私どもにとってもう一つの運命なのです。
パスポートを取る時には、戸籍謄本の提出を義務付けられています。私は特定の日本家族の一員であり、日本のどこで生まれた人間だということを証明する証明書です。両親、家族、地域社会、国家の公民であることを証すこの戸籍謄本がなければ、パスポートは発行してもらえない。
だから、パスポートの背後には、自分が日本人であることが証明されているわけです。国家というものは、その中に生まれた人間にとっては、運命的な存在の枠組みなのです。私たちは親を選ぶことができない。それと同様に国家を選ぶこともできない。国籍変更も今
では条件が整えば可能だ、という人もいますけれども、今度は移籍した国の公民として生きていかざるを得ないわけです。つまり、人間がこの世の中に生まれてきた以上、無国籍者として生きるということはできないようになっているわけです。これ、運命です。
日本とは何か、三つの形容詞
次に、日本とは何かということを考えてみたい。日本という国家は、他国とは異なるどのような伝統を持った国家なのであろうか。
三つの形容詞で日本のことを語るのが一番理解しやすいのではないかと思います。一番目は同質的、二番目は自成的、三番目が連続的です。
〈同質的〉
日本は、広大な海で囲まれた海洋の共同体です。北海道、本州、四国、九州、基本的にはこの四つの島から構成される国土の中で、ほとんど同種の人々が、他国では使われていない、その意味では孤立的な言語である日本語を用いながら生命を紡いできました。宗教上の争いが日本に亀裂を表出させることも、多くはありませんでした。
遺伝子分析が非常に発達してきて、古代の遺跡から人骨が出てきたりすると、その人骨を分析することができるようにもなっています。その結果、日本人は古くから「同質的」であることがわかってきています。日本は淡色です。日本の列島は同じ色なのですね。朝鮮半島に行くと、もういろいろな色が絡み合っているそうです。中国も然りです。世界中で日本は非常に特殊な国です。海に囲まれて外へ行けなかった。外からも来れなかったというような状況があり、同質的な文化と伝統というものを作り上げてきたのでしょう。
さらに言いますと、日本は外国の占領下に置かれたことが一回しかないのです。その一回というのは、ご承知のようにGHQの時代ですから、この七年間を除いて、日本の長い歴史の中で日本が外国に占領されたことはない。同種の人々が孤立的である日本語を用いて、宗教上の争いも少ない同質社会である。世界でも、日本以外にこのような同質社会を探し出すことは難しいようです。
日本も古代の国家形成の時代には、律令制というシステムを導入するために、中国から多くのことを学んだのですが、これも中国の唐王朝が滅亡するあたりから、大陸からの影響力はほとんどなくなったと言っていいと思います。
その中で、日本独自の国家秩序が作られてきた。そして天皇という特有の称号が生まれた。固有の年号が設定されて、国名も日本となった。以来千三百年の歴史が紡がれてきた。同質的な国家としての特徴を千三百年維持してきた。日本は世界史上、類例を見ない同質社会です。
中国史は、王朝の反復転変史です。二十四の王朝が生まれて栄え、滅亡するということを繰り返してきたのです。易姓革命という言葉は聞いたことがあるかもしれません。天子様といわれる皇帝が国を治めるのですが、何年か経ちますとやっぱり国が乱れてくる。農民反乱が起こってくる。そうなると、天命を新たに授けられた徳のある皇帝が生まれてきて、またその統治を始める。そのようなことを二十四回繰り返してきたわけです。革命は、命(めい)を革(あらた)めると読みます。徳を失った皇帝は、新たに天命を授かった支配者によって、命を革められる。これが革命です。
二十四回も反復転変があったのですが、反復転変を正当化する易姓革命論が、中国の歴史の中に埋め込まれていると言ってもよいと思います。このように言えば、一九四九年に生まれた現代の中華人民共和国も、一つの新しい王朝だと言えば言えないことはない。あるいは毛沢東王朝、習近平王朝と、後世言われることになるのかもしれない。
中国の万里の長城に行かれたことがあると思いますが、どうしてあんなものを造ったのでしょう。信じられないくらい巨大な構造物です。漢民族は、北方の遊牧民族や騎馬民族との抗争を何回か繰り返してきた。そのための抵抗の象徴です。中国には、騎馬民族や遊牧民族が中国に入ってきて、漢族を支配したという歴史があります。一番我々の身近に感じるのは、モンゴル、元朝です。それから清国です。清朝、これ女真族の作った征服王朝です。元朝とか清朝などは異民族による征服王朝です。
〈自成的〉
二番目に自成的と言いました。対句は他成的です。これは人類学の用語です。オートジェニック、つまり日本の社会の発展は同質社会の発展です。自ら成ったものだということです。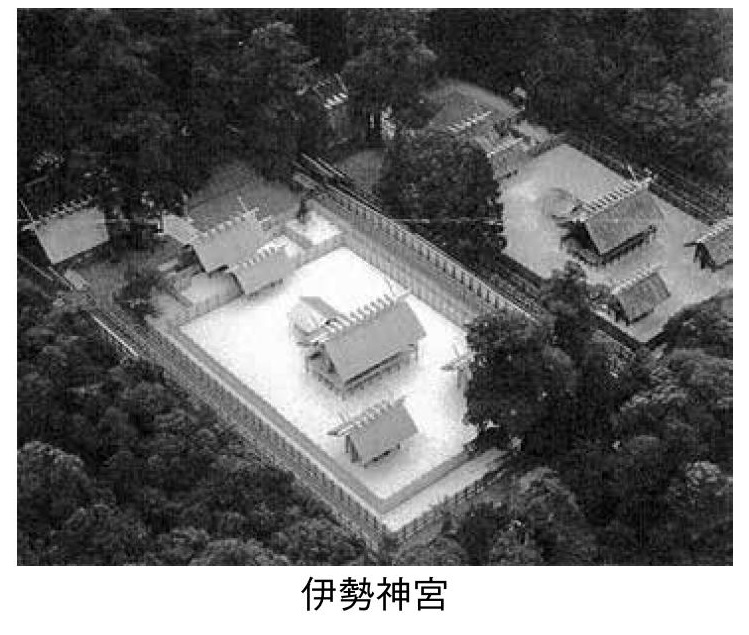 中国の発展は他成的です。異民族、騎馬民族、満洲族等によって征服されて生まれた王朝です。異質社会である中国の発展は他成的、つまり他文明の影響を徹底的に受けて形成されたものだと言えます。日本とは全然違います。故宮博物館に行くと、中国においていかに清朝・モンゴルの影響力が強かったかということを随所に見ることができますが、日本人にはなかなか信じられないような話だと思います。
中国の発展は他成的です。異民族、騎馬民族、満洲族等によって征服されて生まれた王朝です。異質社会である中国の発展は他成的、つまり他文明の影響を徹底的に受けて形成されたものだと言えます。日本とは全然違います。故宮博物館に行くと、中国においていかに清朝・モンゴルの影響力が強かったかということを随所に見ることができますが、日本人にはなかなか信じられないような話だと思います。
異民族による征服とか、あるいは権力内部における反乱とか、そういったものに彩られた歴史が中国の歴史です。私は中国、朝鮮半島の歴史の方に比較的詳しいのですが、朝鮮半島の歴史は同族相(あい)食(は)むの歴史です。結局、朝鮮の歴史は血族団の抗争史として描き出すことができるというようにさえ思っております。日本と、朝鮮・中国は、そういう意味で、徹底的に異質です。
〈連続的〉
日本の歴史が連続的だということを示そうとして、お伊勢様の式年遷宮のことを思い起こしました。二十年ごとに内宮と外宮の二つの正殿と十四の別宮を完全に造り替えて、神座を移すことをやってきたのです。ですから、この写真で見ますと、右上の方が古いです。これを、全く同じように新しいものに造り変えるわけです。二十年に一回、でも二十年も経つとこれも古くなりますから、また同じことを繰り返すわけです。
調べてみると、お伊勢さまの式年遷宮は持統天皇治世の時代、六九〇年に始まっているのです。平成二十五年の式年祭は、数えて六十二回目で、その間実に千三百年の歴史が流れている。千三百年の間に六十二回行ってきたわけです。日本人は、一体どうしてこんな厄介なことをやり続けてきたのでしょうか。誰も答えてくれる人はいないと思うのですが、日本の歴史の連続性というものを、確認するための催しだったのかもしれません。
私に答えがあるわけではありませんが、こういう祭事をなんとか守り続けようという民衆の意思があって、日本の歴史が連続的なものになったと言えるでしょうし、あるいはその連続性を確認しようとして、このような分かりやすい催しをやったのかもしれない。誰も答えを教えてくれていないのですけれども、そういうことではないかと、私は考えているわけです。
皇室の存在と一世一元制の意義
連続性の話になりますと、当然、皇統のことになります。現在の令和の陛下は百二十六代です。万世一系。少なくとも、我々が持っている共通のイメージとしては万世一系です。このような存在を、他の国々の皇室や王室の中に見出すことは不可能です。
日本の憲法では、「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と書かれています。確かにそれはそうだと思うのですが、私はそれだけではちょっと足りないのではないかという感じは持っているのです。むしろ、「天皇は日本という国家と民族の連綿として続く歴史の象徴だ」という観念が、この中に入ると良いかなと思うのです。
明治、大正、昭和、平成までが過ぎ去って令和がやってきているわけです。この間、一世一元の制です。一人の天皇は一つの元号を持つという一世一元の制です。これはまことに優れた制度設計ではないかと思うのです。皇室(天皇家)の血脈が瞬時たりとも途絶えることなく紡がれていることが、これによって証されてるからです。
曽祖父母があり、祖父母があり、父母があって自分があるという私どもの血脈の連続性を、天皇家の血脈の連続性の中にプロジェクションとすることができる。それが故に、天皇家の血脈の連続性は尊いものであると思うのです。
つまり、私固有の考え方で言わせていただきますと、「限りある個々の人間の人生が、代々と続く血脈の中にある」。そういう連続性を私どもに直感させるものが、一世一元の制にあるのではないか、というのが私の考え方です。
最後に、内藤鳴雪というアララギ派の俳人、正岡子規の弟子です。その鳴雪の句に、
元日や 一系の天子 不二の山
という名句があります。冬の富士山という真っ白い自然の大きな塊の中に、神々しいものを感じ、そこに一系の天子を仰ぎ見るという感覚、これは天才でなければできないのでしょう。