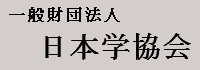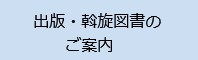『日本』令和7年5月号
憲法改正を阻んできた〝学習性無力感〟というくびき
渡邊 毅 /皇學館大学教授
岸信介の宿願
日本国憲法が施行されて、今年で七十八年になる。この間、第九十六条に定められた改正の手続きが、実行されたことは一度たりともない。これは、「制定以来、全く改正されていない憲法」として世界最長記録になっている。通常、他国では憲法の一部を「改正」や「修正」という形で柔軟に変えていくことが多く、日本のように「一切改正なし」というケースは非常に稀なのである。
では、なぜ日本では憲法改正(修正も)が実現しないのか。その問いに答える鍵を探すには、昭和三十年代にまで遡る必要がある。
戦後の日本において、憲法改正を最も現実的な課題として推し進めようとした政治家がいた。岸信介元首相(一八九六~一九八七年)、その人である。岸は当時、どの政治家よりも、安全保障、外交、内政、経済、そしてそれらの大本にある憲法改正までを包括する明確かつ強烈な脱戦後構想を持っていた。岸の最大の目標は憲法改正にあり、実質的な主導者として内閣に憲法調査会を設置するなど改正の基盤作りを進めていた。岸内閣発足後の国会答弁でも、「私は個人として憲法改正論を抱いております」と述べ、改憲の立場を明確に示している。
岸は自民党を率い、安保条約改定を成し遂げるなど戦後日本の体制再編に大きな役割を果たしたが、憲法改正に関しては、左派勢力の反発や野党の強い抵抗(三分の一超の議席を獲得したこと)、さらにはアメリカの意向など、複数の要因により実現には至らなかった。
岸は退陣直前に暴漢に襲われ瀕死の重傷を負ったが、それ以後もなお憲法改正を長期的な課題として捉え続けた。特に、彼の後継者である佐藤栄作(実弟)や中曽根康弘といった政治家たちに影響を与え、自民党内で改憲の議論を継続させる役割を果たした。岸自身は「憲法改正には最低でも三十年かかる」と述べており、長期的な視点で憲法改正の土台作りに努めたのだった。しかし、岸の存命中に憲法改正が実現することはなかった。
「何をやっても無駄だ」と学んでしまう学習性無力感
この挫折は、後の政治家たちに対して「憲法改正を進めることは、極めて政治的リスクが大きい」という印象を強く植えつけ、岸の後を継いだ池田勇人元首相に早くも「憲法改正を行う考えは毛頭ない」と言わしめている。これ以後、憲法改正の動きに長期的な影響を与え、改憲に慎重になる姿勢を定着させてしまったのだった。
岸は戦後日本の政治家の中でも極めて強いリーダーシップを持ち、「昭和の妖怪」とも呼ばれるほどの人物だった。その岸ほどの政治手腕を持ち、強行採決も辞さない強硬な姿勢を取ることができた政治家でさえ、憲法改正には手をつけられなかったという事実は、戦後の自民党政治の中で重くのしかかるものとなったのである。
心理学者マーティン・セリグマンは、実験的研究によって「学習性無力感」を発見しているが、岸以後の政治家(安倍晋三元首相を除く)は、この無力感のくびきから逃れられなかったのではないかと考えられる。学習性無力感とは、繰り返す失敗や制約を経験することで、「何をやっても無駄だ」と学習し、主体的な行動を諦めてしまう心理状態を指す。セリグマンの実験では、回避不能な電気ショックを受け続けた犬は、その後逃げ出すことが可能になった環境下でも、行動を起こさなくなることが示された。
これは、人間でも引き起こされることが分かっている。学習性無力感を抱いていると、目標は手が届かないものと感じられ、行動可能なこともできなくなってしまう。無力感を感じてしまった対象には、自分の力ではコントロールできないと考えるので、頑張る決意を極限まで弱くしてしまうのである。
これを、岸の憲法改正に照らせば、その挫折は電気ショックのように、その後の政治家や国民に打撃を与え、「改憲は無理だ」と学習させ、結果として憲法改正に対する無力感を生み出してしまったのではないだろうか。この挫折は、岸以降の保守政治家に強い影響を与えた。彼の後継者たちは、憲法改正を党是としながらも、改憲に正面から取り組むことに慎重になり、結果として憲法改正の試みは長期にわたり停滞することとなったのである。憲法改正は置き去りにされたまま、経済大国への道をひた走ることになるのである。
さらに、国民の意識にも学習性無力感が浸透した可能性がある。岸の時代に見られた激しい政治対立や社会運動の記憶が「憲法改正を議論すること自体が混乱を招く」という印象を生み出し、多くの人々が改憲問題を避ける傾向を強めた。その結果、憲法改正は「非現実的な目標」と見なされるようになり、政治的な争点としても優先順位が下げられることとなった。
無力感は克服し改正へ
しかし、学習性無力感の研究が示すように、一度獲得された無力感は必ずしも不可逆的なものではない。新たな成功体験や環境の変化によって、それを克服することが可能である。セリグマンによれば、無力状態がすぐに消える人とそうでない人との差は、「挫折を永続的で普遍的なものと解釈するかどうか」「希望があるか、ないか」であるという。
近年、憲法改正をめぐる議論が再び活発化している背景には、時代の変化とともに無力感が払拭されようとする動きがあると考えられる。特に、安全保障環境の変化や国際社会における日本の立場の変化は、改憲論議を再燃させる要因となり、岸の意志を継いだ孫の安倍が、それを背景に憲法改正のための議論を政治の中心課題の一つとして推進していったことは、戦後政治におけるめざましい出来事であった。改憲のための国民投票法の成立、検討会の設置や国会での活発な議論の促進、そして安全保障政策の転換といった具体的な取り組みは、直接的な改憲は実現しなかったものの、関連する法制度の整備や議論の再活性化といった点で一定の成果を挙げ、将来的な改正に向けた基盤作りに大いに寄与したと評価できる。
安倍は、「憲法改正は決してたやすい道ではありませんが、必ずや私たちの手で、私の手でなし遂げたい」(令和二年十二月九日)と五年前、記者会見で述べていた。このような希望と不退転の決意があれば、改憲は決して不可能なことではない。岸の改憲を阻止した一つの要因に改正手続き(国会両院の三分の二の賛成が必要)があったが、それも断念する程のものではない。「三分の一の壁」などと、ことさら強調するまでもないことだ。
現に、そうした制約はドイツやアメリカと変わらないのだ。ドイツ憲法(基本法)では改正のために両院の三分の二の賛成が必要とされ、アメリカでも両院の三分の二に加え全州の四分の三の議会での賛成が必要になっている。アメリカの改正手続きは、日本よりもなお厳しいと言える。それでも、現在までにドイツ六十七回、アメリカ二十七回と改正が行われているのである。
改憲の不可能性は、決して「永続的で普遍的なもの」ではない。改憲の実現を左右するのは、「希望があるか、ないか」である。今後の選挙により、改憲勢力が再び衆参ともに三分の二を超える時期が到来する可能性は十分にある。改憲は、もう手の届くところに来ているのに、動かないだけなのだ。改憲には、政治力、総理大臣の指導力によるところが大きい。無力感を克服し、首相自らが確固たる決意と覚悟で意志を党内に示していけば、まちがいなく前進するだろう。
だが、最終的に投票で改憲できるのは、首相ではなく主権者である国民だ。憲法に対する国民の理解の深まりも改憲には欠かせない。かつて改憲に関しては、イデオロギーや歴史認識が絡むことが多く、しばしば国民間で対立を生んできたが、今やそうした事態は、過去のもの―左派野党とマスコミの妨害は除く―となった。朝日新聞(令和六年五月)の調査でさえ憲法改正が必要と考える人は六三%に達し、多数派になってきている。時代思潮は、ここまで変わってきているのだ。日本の歴史・伝統を知らない二十四人のアメリカ人が、たった一週間で書き上げた翻訳憲法を「不磨の大典」のごとく祀り上げるのも、もうわずかな人たちに限られるだろう。
もう一度言おう。改憲を阻止してきた根本は、実は政治家も含め国民の無力感だったのだ。それに気づき、改憲に向けて岸と安倍が示した希望と勇気を私たちは静かに、しかし確実に引き継ぐ覚悟が求められている。彼らが直面した困難や逆風に学び、私たちもまた恐れずに語り、行動することが必要だ。未来を他人任せにせず、主体的に築く責任が、今まさに問われているのである。