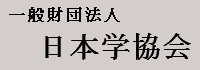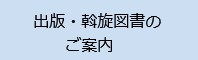『日本』令和7年10月号
大東亜戦争の淵源 ― 資料が語るその史実 ―(十)アメリカが攻撃を受けない限り参戦しない
田村一二
一 第二次世界大戦の勃発とドイツの優勢
ルーズベルトは隔離演説後、孤立主義者の猛反発を受け、改めて「孤立・中立主義の世論の強さ」に直面しました。そして、演説は孤立・中立路線を逸脱したものではないと繰り返し国民に訴えますが、その一方においては、何事もなかった如く政策を孤立・中立路線に回帰させ、職務に専念します。しかし、外交政策を転換したか否かの論争は長く続き、こうした状況の下、一九三七、三八年が過ぎていきました。
翌一九三九年九月一日、ドイツとポーランド間のダンチヒ回廊を巡る交渉が決裂して、ドイツはポーランドに侵攻して、ヨーロッパ大戦が勃発しました。英・仏はポーランドの後押しをしたものの、ドイツとの戦争には消極的でした。しかし、背後にはルーズベルトが控えて居り、英・仏を威圧し無理やり開戦を強いていたのです。同大戦の勃発にはルーズベルトが深くかかわっていました(タンシル『裏口参戦・下』三四八 ―三五三頁)。
三日、英・仏はドイツに宣戦布告をして、第二次世界大戦へと突入していきます。同日、ルーズベルトは、すかさず「合衆国がこの戦争に巻き込まれずにいることを願っている」、続いて五日、中立宣言を発布します。その後も、戦争回避の保障を繰り返し行い、十月二十六日、ラジオ放送で次のように言い切り、中立を堅持する大統領の方針を信頼するよう訴えました。
いかなる形態、方法、形式であれアメリカの母親たちの息子たちを、ヨーロッパの戦場で戦うために派遣する可能性など、これっぽっちも提案したことは一度たりともない。アメリカは中立であり、戦争に関わるつもりもない(ビーアド『「戦争責任」はどこにあるのか―アメリカ外交政策の検証』三五九頁)。
その後、ドイツ軍と連合国軍とは戦争中だが戦闘のない状態が八カ月以上続きますが、翌四〇年五月十日、突如としてドイツ軍は雪崩を打って、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクに侵入し、またドイツ西部のマジノ戦線を突破して北フランスにも進撃していきました。ドイツ軍は、破竹の勢いで五月末にはイギリス軍をフランス最北端のダンケルクまで追撃して、遂にイギリス本島へと追い落としました。
六月、パリ陥落、続いてベルギー、オランダ、デンマーク、ノルウェーは、ドイツの支配下におかれ、イギリスは孤立して風前の灯火となりながらも、たった一国で生存をかけてドイツと戦っていました。
前述(第九回)のように一九三七年十二月には、アメリカは、既にイギリスとの軍事的擦り合わせを行っていたものの、イギリスが孤立無援の窮地に陥り、首相チャーチルの悲痛な叫びがルーズベルトに届いていても、表むき大統領は尚、孤立主義・中立路線の姿勢を崩すことはありませんでした。
二 第三期大統領選挙の二つの誓約
アジアでは支那事変、ヨーロッパでは第二次世界大戦と世界の騒乱の中で一九四〇年、アメリカは大統領選挙の年を迎えます。
民主党は七月、史上初の第三期大統領候補者としてルーズベルトを指名しました。一方、共和党は八月、ウェンデル・L・ウィルキーを大統領候補者に指名しました。両陣営の選挙戦最大の課題は、反戦・平和の方針をいかに国民に示し、支持を得るかにありました。
民主党は綱領で次の反戦条項(誓約Ⅰ)を決定して、更にルーズベルトは選挙演説で大統領として、もう一つの誓約(誓約Ⅱ)を国民と交(かわ)わします。
資料―七月・民主党綱領/反戦条項
党の誓約(誓約Ⅰ)
われわれは外国の戦争に参加することはありません。われわれは、攻撃を受けた場合を除いて、わが国の陸、海、空軍をアメリカ大陸以外の外国の地で戦わせるために派遣することはありません。 (ビーアド前掲書、四〇一頁)
資料―十月・ボストン演説大統領と国民との誓約(誓約Ⅱ)
母親であり、父親である皆さんに向けて、私はもう一つ保証します。以前にも言いましたが、何度でも、何度でも言います。あなた方の息子たちが外国の戦争に送りこまれることは決してありません。わが国の防衛の目的は国を守ることです。 (同 四三一頁)
共和党綱領の反戦条項は、次の通りです。
共和党はこの国を外国の戦争に巻き込むことに断固反対します(同 四〇一頁)。
㈠ 資料の意義
共和党綱領は、無条件で、明解に、反戦を宣言しています。一方、民主党綱領(誓約Ⅰ)は「攻撃を受けた場合を除いて」と条件を付けた上で、反戦を保障しているもので、「攻撃を受ければ」参戦するのです。この条項はあたり前の文言に聞こえますが、やがてルーズベルトの外交・軍事政策を制約していくのです。
選挙戦の後半、ウィルキーが有利となり、ルーズベルトの当選が危なくなってきました。そのため、さらに一歩踏み込んだ「厳粛な約束」を国民と交わさざるを得なくなります。それが誓約Ⅱです。そこには一切の条件を付けず、大統領は「参戦しない」と国民と誓ったのです。これは当選せんがために「心ならずも」国民と交わしたものです。
この資料はルーズベルトの本心がどうであろうと、アメリカ大統領選挙の公約が、政治生命に直結する重さを持っていることを示すものです。
㈡ 解説⑴ 民主党反戦条項が決定するまでの紆余曲折
民主党内には戦争介入派と反戦派があり、最終的に反戦派が優位に立ち、綱領策定小委員会では、「われわれは外国の戦争に参加することはありません。そして我が国の陸、海、空軍を、アメリカ大陸以外の外国の地で戦わせることに派遣することはありません」という反戦政策を決議して、直ちに担当部門に報告し、党綱領案として全体委員会に提示しました。
戦争介入派からは激しい攻撃を受けたものの、反戦派の大多数の支持を得て、党大会に提出する綱領の案が出来ました。しかし、何としても巻き返しを図りたい戦争介入派は、一見無害な文言、「攻撃された場合を除いて」を追加することによって「党の調和」を図りたいと提案して、妥協を申し入れました。合衆国が攻撃されれば戦うことは、全委員が一致しており、強硬な反戦派で反戦条項提案者のウィーラー上院議員は、修正を受け入れました。
⑵ 反戦条項を不快に思うルーズベルトこの妥協案ですらも、ルーズベルトは不満をもっていました(ビーアド前掲書、三九六頁)。戦争介入派は、反戦条項作成者のウィーラー上院議員に更なる修正を求めますが、同議員は拒否し、「もし全体委員会で重要反戦条項が変更されれば、党大会から退席する」 と応答します。こうして制限付きの反戦条項は民主党の選挙綱領に組み込まれたのです。
綱領を自分の思い通り書きたいと望んでいたルーズベルトは、この成り行きを不快に思っていました。その証拠に一九四〇年七月、指名受諾演説でもこの綱領には言及せず、この国を戦争に巻き込まないという決意も明言しなかったのです。その代わり、「今、差し迫っているかもしれない不測の事態」について、アメリカ国民に警告し、危機感を煽ったのです。
⑶ ウィルキーの非難とルーズベルトの反撃大統領選が本格的となってきた九月、ウィルキーは、「自分が大統領に選ばれれば、アメリカの青年をヨーロッパの修羅場(戦場)に送ることはない」と幾度も国民に訴え、返す刀でルーズベルトの誠意に対する疑義、即ち一九三九年、チャーチルの英国海相時から始まり、首相となっても続いている秘密書翰の交換後注について、「大統領は合衆国を戦争に参加させることで他の国と秘密合意を交わしている」(ビーアド前掲書、四一三頁)と激しく追及し、非難しました。
非難の究極は十月三十日、メリーランド州の都市で、「もし、大統領が約束を守らなければ、今日、徴兵召集されたメリーランド州の青年たちの一部は、直(ただち)に輸送船に乗り込むことになる」。さらに同日午後には、「大統領が過去に国民とした誓約が長続きしたのか」と疑問を投げかけた上で「彼が再選されれば、一九四一年四月には我が国は戦争している」と大統領の信義のぎりぎりのところまで攻撃したのです(ビーアド前掲書、四二一―四二二頁)。
一方、ルーズベルトは迫りくる戦争の危機は力説するものの、今まで反戦条項に触れるのを避けてきました。そして九月、二ケ月も前に採択されていた「攻撃された場合を除いて…」という反戦条項にようやく言及して、国民に訴えたのです。しかし、時はすでに遅く世論調査は、ウィルキーの優勢を示していました。
危機感を持ったルーズベルトは、反撃に出ます。投票日も迫る十月三十日、ボストンで「攻撃を受けた場合を除いて」などの但し書きを一切とり去った、最も厳しい「無条件で厳粛な約束」、即ち誓約Ⅱを、国民と交わしたのです。さらにルーズベルトは投票日直前の十一月二日、バファローで、「皆さんの大統領は、この国は戦争に向かっていないと言っている」と、平和を保障します。
このこれらの演説は、群衆の熱狂的な歓呼を浴び、ルーズベルトは大統領選挙戦を勝ち取り、史上初の第三期大統領に当選します。アメリカ国民と交わした二つ誓約は、国民は勿論、ルーズベルト自身も決して頭から離れることなどなく、故にルーズベルトは、苦悶しながらも、真珠湾事件の「からくり」を構成せざるを得なくなるのです。
三 選挙公約の微妙な修正
選挙の熱気がまだ冷めやらぬ十二月二十九日、この平和の保証に疑念を抱かせる次のような炉辺談話を発表しました。その内容は、「イギリスとその同盟国は、枢軸国と勇敢に戦っている」と述べた上で、次のようにアメリカ国民に語ります。(要旨)
われわれ自身の安全は、そうした戦いの結果によって大いに左右される。アメリカが枢軸国から自国を守るために、今やる事すべてを行えば、戦争に巻き込まれる可能性は低くなる。しかし、いかなる道を選んでもリスクはつきものである。もし、イギリスが崩壊すれば、ナチスはアメリカの安全を脅威するに違いない。その為にアメリカは進んで民主諸国の軍需工場となり、武器弾薬を大量に供給せねばなりません。故に「われわれは、民主主義の偉大な武器庫でなければなりません(We must be thegreat arsenal of democracy)」。
( 原典、アジア歴史資料センター、レファレンスコードB02030751600、炉辺談話、一二三―一四三頁)
「どの道を選んでもリスクはつきものである」と警告を発し、その言葉は「アメリカは戦争に向かっていない」との約束に疑念を抱かせる文言でした。 同年六月以降、イギリスは、ドイツの猛攻に晒(さら)されており、イギリス首相チャーチルは、悲痛の思いでルーズベルトに武器援助を求め続けていました。ルーズベルトの心中には、一日でも早くイギリスを救援したいとの考えが当然あったでしょう。だからこそ、アメリカが「今できる事」として、「民主主主義の偉大な武器庫」になるという炉辺談話を発表したのです。
果たせるかな、炉辺談話の翌日、ルーズベルトは、モーゲンソー財務長官らをホワイトハウスに呼び、イギリスへの具体的援助、即ち「武器貸与法案」を協議したのです。モーゲンソーは後年、この法案がいかにして生まれたかについて、次のように語っています。
チャーチルからルーズベルト宛に手紙(一九四〇年十二月七日付)が届いた。その手紙は、ルーズベルト大統領が言うところの「ドル記号($)」の付かない形でのアメリカからイギリスへの援助を提案したものだった。ここに至ってモーゲンソー氏は、ルーズベルト大統領がチャーチル首相のアイディアに賛同し、これを発展させて、こうして一九四〇年十二月三十日、ホワイトハウスの会議室で武器貸与法案は生まれたのだった、と。(ビーアド『ルーズベルトの責任』四七頁)
「ドル記号のつかない形」での援助とは、「金額に制限を設けない援助」であり、この法案がとてつもない法案であることを意味しています。
武器援助の意味するところは、今のウクライナとロシアの戦争を見ればわかることですが、ウクライナが戦争継続できているのは、アメリカとヨーロッパ諸国の莫大な資金と武器の援助があるからです。武器援助法案とは、「武力以外の参戦」を意味するのです。
四 武器貸与法―真珠湾事件への道標
こうして一九四〇年が終り、一九四一年、ルーズベルト大統領は、アメリカ国民との誓約に道義上の責任を抱えたまま新年を迎えます。
年末に布石を打っておいた「民主主義の兵器庫」構想を具体化した「武器貸与法案」が一月十日、連邦議会に提出されました。
提出された原案の大きな問題点は、「大統領が合衆国の防衛に重要だと判断すれば、援助する国、武器の種類・数量、期間等」を、「他の法律の規定に関わらず」意のままに援助を実行出来る権限を大統領に与えるものでした。通過すれば、共産主義国・ソ連にも武器援 助ができるのです。
それよりも更に重大であったのは、「護送問題」でした。即ちイギリスを始めとする援助国に無事物資を届けるためには、枢軸国の潜水艦が群がる大西洋を横切らねばならず護送が必要です。
法案審議では、アメリカ海軍艦艇が護送するなら、それ自体が戦争行為ではないか、それは大統領に戦争へ踏み出す権限を与えることではないかとの、大議論を引き起こします。つまり平和か、戦争かの問題に直結している故に、三カ月にわたって激しい論争が展開されることになりました。
法案の支持者は、法案を何としても通過させるために、「この法律のどこをとっても」、「合衆国海軍の艦艇が護送することを認可するものではない」、「アメリカ船舶が戦闘地域に入ることを認可するものではない」、さらに、「合衆国陸海軍の動員に関する法律を変更する ものではない」との趣旨を追加しました。
追加条項は、護送と交戦を禁じるもので、「この法律を遂行するにあたって、大統領は軍隊に戦争行為を命じることはできない」と規定するものです。
このように幾つかの修正を経た後、下院では賛成二六〇票、反対一六五票。上院では賛成六〇票、反対三一票の大差で可決され、一九四一年三月十一日、大統領の署名をもって立法化されました。
武器貸与法の成立は、大統領の歴史的勝利であり、チャーチルはそれを第二次世界大戦の「第三の頂点」と呼んだほどです。チャーチルが言う大戦の五つの頂点とは、第一がフランスの敗北、第二がイギリスの対独戦闘、第四が独・ソ開戦、第五が真珠湾です。この頂点は、いずれもルーズベルトの世界戦略の節目となっています。「イギリス援助」の固い決意を持ったルーズベルトは、国民と交わした誓約の壁に一穴をあけて、「真珠湾への道標」を一歩一歩踏み超えていくのです。
〔後注〕
ビーアド『ルーズベルトの責任』三五七―三六七頁。「ルーズベルト大統領とウィンストン・チャーチル英首相との間で交わされた秘密往復書簡の問題」で詳述している。
さらに、秘密合意が事実であることは、一九四五年四月、チャーチル自身がルーズベルトの追悼演説で明らかにしています。更に武器貸与法の考案やその目的についても語っています。追悼演説の抜粋は次の通りです。
〇 一九三九年九月、私が海軍省に移りますと、彼から電報が届きました。私の気が向けばいつでも、海軍やその他の問題について直接連絡するように言ってくれたのです。首相の許可を得て私はそうしました。
〇 私は彼にわが国の海軍の動向や様々な活動について、一連の情報を流しました。
〇 私が首相となり、戦争が激化し我々の生活と生存が危機に瀕したとき、私は既に大統領とは最も緊密で、私にとって最も好ましくもある交友関係のもとで、彼に電報を打つことができる仲になっていました。
〇 このような通信は一七〇〇通を超えるものになっていましょう。
〇 同じころ、彼は武器貸与法と呼ばれる援助の非常方法を考案しました(前述のモーゲンソーの発言とは異なる)。この法の目指すところは、主として英国の戦闘力の増大にあり、戦闘努力のあらゆる目的のために我々は、いわば、はるかに優勢な共同体たらしめるにあったのです。( )は筆者
( ビーアド前掲書、三九七―三九八頁。及びチャーチル著『第二次大戦回顧録・第二十三巻』毎日新聞社翻訳委員会訳、二三二―二三六頁、同社刊)