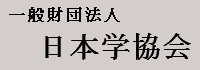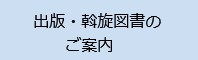『日本』令和7年10月号
「志の教育」への期待
橋本秀雄 /日本教師会事務局長
青少年の憂ふべき実態
我が国の年間出生数は、第二次ベビーブームの昭和四十年代後半に、二百万人を超えてゐたのをピークとして、その後、ほぼ毎年減り続け、昨年初めて七十万人を下回つた。人口が国力の基礎であることを思へば、子供が少ないだけより立派に育つて欲しいと願ふのだが、逆に問題が少なくないのである。
また、青少年の意識も問題である。昨年四月、日本財団が「十八歳意識調査『第六十二回国や社会に対する意識(日・中・韓・印・米・英の六カ国)』」を報告した。主なものをあげると、自国の将来について「良くなる」と回答した人は、中国八五・〇%、インド七八・三%、韓国四一・四%、アメリカ二六・三%、イギリス二四・六%、日本一五・三%と、日本の青少年は悲観的である。自国について「機会があれば留学や他国で就労してみたいと思う」が、韓国七九・三%、イギリス七六・七%、インド七六・一%、中国七二・六%、アメリカ七一・五%、日本五二・八%と、内向きである。また「自国は、国際社会でリーダーシップを発揮できる」は、中国九五・〇%、インド八五・四%、アメリカ六六・五%、韓国六一・五%、イギリス六〇・一%、日本四一・一%と、自信がない。
新堀通也氏の「志の教育」
今から二十五年前、「心の教育」や「生きる力」について単なるスローガンに終はるのではと警鐘を鳴らしてゐた人がゐた。教育社会学者の広島大学名誉教授新堀通也(しんぼりみちや)博士である。
ただ、その考へ方は、「志」といふ言葉に「維新の志士」「悠久の大義を志す」といつた戦後社会で受け容(い)れ難い言葉と結びつけられたためか、学校現場に広がつていかなかつた。
「志の教育」の実践
その一つが、第六十一回日本教師会教育研究大会(令和五年八月、岐阜市)で東京都世田谷区立の小学校の伊藤優教諭が発表した「子どもの志を育む教育」の実践である。
先生は、日本の子供達の現状を、「自分に受け継いだ命の価値に気付かず、生きる意味を見失い、誇り高い生き方をした先人たちを知らずに育った結果ではないか」と考へた。それは先生自身が小学校の頃に、「日本はアジアを侵略した悪い国だと教わり、日本が嫌いになったからだ」といふ。大学生になつても自分の命の尊さを感じることもなく、なぜ生きるのかに悩んだのである。そんな時、先生は祖父の生ひ立ちを知つた。祖父はシベリア抑留を経験し、酷寒の地獄のやうな生活を生き延びた一人であつた。自分の命は祖父が必死になつて生きてくれたお陰であり、祖父やシベリアで亡くなつた同朋の方々にいただいた命を大切にしなければならないと気付いたのである。その命はさらに日本の先人が様々な困難を乗り越えて自分に伝へてくださつたものであり、先人はどのやうな思ひで日本を築いてこられたのかを知ることが、生きるエネルギーになると考へられた。以来、授業や朝の会・帰りの会などの時間に、偉人がどんな志をもつて生きたかを語られた。その話に感動した子供達は、自分も志をもつて生きたいと言ふやうになり、授業や諸活動に懸命に取り組むやうになつたのである。
先生は、「吉田松陰の教育観を現代にどう活かすかを考察し、子どもたちに日本人としての誇りと志を取り戻させる教育のあり方」を提案した。先生は幼少時から親や教師の導くままに努力し、順調に過ごしてきたが、大学生になり自分は何のために生まれたのか、何をしたらよいのかに悩んだといふ。卒論テーマも浮かばず、鬱状態となり自殺まで考へたが、両親の顔が心に浮かび、思ひ止まつた。この経験から、子供達に同じ思ひをさせてはならないと、教師の道を志し、吉田松陰の教育理念が教育の現状を救ふと感じ、以後、「大和魂教育」「立志教育」など七つの柱をたて、子供達に自分は日本人であるといふことを自覚できるやう、祝祭日の意味を教へたり、偉人の生き方を紹介したりしていつた。また、自由主義史観の斎藤武夫氏の歴史授業に学び、常に日本人の視点から歴史をとらへる授業を行つた。教科書の出来事をなぞるだけでなく、その人物の立場に自分が立つたらどうするか、と主体的に考へていくのである。子供達は先人の思ひや努力に気付き、日本に対する誇りや自覚をもつやうになつたといふ。
「生きる力」を実現する「志の教育」
現在、学習指導要領は「生きる力」を育てるために、「主体的・対話的深い学び」を通して子供達に問題を見つけ自ら解決する力をつけようとしてゐる。それは望ましいことではあるが、知的な学びはできても、今求められる自立心やたくましい心を育むことは難しい。今日の危機を乗り切るには、まづ国家社会の危機を認識する必要がある。新堀博士は社会そのものが生き残ることが難しいのに個人だけが生き残ることはあり得ない。生き抜く力は個人と社会、表裏一体であると言はれる。現在及び将来の社会の危機を認識し、それを打開することに自らの使命や責任を見出すことが必要であり、それができたら自分の価値を確認することになり、真に「生きる力」をもつことになる。それが「志の教育」なのである。
期待された伊藤先生は、惜しいことに病で亡くなられた。しかし、小出先生は自ら研究会を組織し、各地で講演と実践交流を精力的に行つてゐる。今後、「志の教育」がさらに広まることを願つてやまない。